突然、理由もなく胸がざわざわしたり、息苦しさを感じたりする不安感に襲われた経験はありませんか?
こうした急な不安感には、心の問題だけでなく身体や生活習慣の影響も関係していることがあります。
この記事では、不安感の主な原因や関連する病気、適切な対処法について、初心者にもわかりやすく解説します。
急に不安感に襲われるよくある原因とは

急な不安感には、日常生活に潜むさまざまな要因が関係しています。
まずはよくある原因を見ていきましょう。
ストレスや緊張がたまっているから
仕事や人間関係、将来への不安など、ストレスが積み重なると心の余裕がなくなります。
知らず知らずのうちに緊張が続き、ふとしたときに急な不安感として表れることがあります。
これは「自律神経の乱れ」によって、体が過剰に反応してしまうためです。
厚生労働省でもストレスと健康の関係について解説しており、メンタルヘルス対策の重要性が指摘されています(厚生労働省|こころもメンテしよう)。
過去のつらい経験が影響しているから
過去のいじめ、事故、災害、失恋など、心に傷を負った経験があると、類似した状況に再び遭遇したときに不安感が強く出ることがあります。
これは脳が「また同じようなことが起きるかもしれない」と過剰に反応してしまう防御反応の一つです。
心理学では「トラウマ反応」と呼ばれ、PTSDなどにもつながるリスクがあります。
つらい記憶が思い出されやすくなることで、突然の不安感につながるのです。
ホルモンバランスの変化があるから
特に女性は、生理前後や更年期にホルモンバランスが大きく変化します。
これにより気分が不安定になり、不安感が強まることがあります。
エストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンは、感情を安定させる脳内物質の分泌にも関与しています。
ホルモンの影響は更年期障害とも深く関係しており、婦人科での相談も有効です(日本産科婦人科学会|更年期障害について)。
カフェインやアルコールのとりすぎだから
コーヒーやエナジードリンクに含まれるカフェインは、脳を刺激して覚醒させる作用があります。
しかし過剰にとると心拍が早くなったり、動悸が出たりして不安感につながることがあります。
アルコールも一時的にはリラックス効果がありますが、代謝後に反動で不安が強くなることがあります。
不安感が強いときは、カフェインやアルコールの摂取を控えることが勧められます(e-ヘルスネット|アルコールと精神健康)。
急に不安感に襲われるストレスとの関係を解説
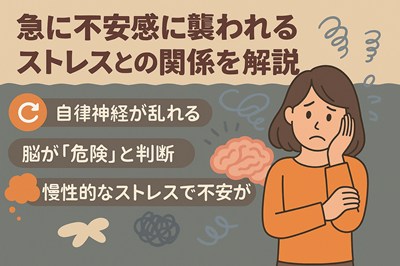
不安感とストレスは密接に関係しています。
ストレスがどう影響するのかを理解することで、より良い対処が可能になります。
ストレスで自律神経が乱れる
自律神経は「交感神経」と「副交感神経」のバランスで成り立っています。
交感神経が優位になると、体は緊張状態となり心拍数や呼吸が早くなります。
慢性的なストレスによってこのバランスが崩れると、突然の不安感につながることがあります。
ストレス軽減のためには、規則正しい生活やリラックスできる時間の確保が重要です。
脳がストレスを「危険」と判断する
ストレスが続くと、脳の「扁桃体(へんとうたい)」という部分が敏感になります。
扁桃体は恐怖や不安を感じる場所で、ここが過剰に反応すると、実際には安全な状況でも「危険だ」と感じてしまいます。
つまり、脳が常に戦闘モードになっているような状態になります。
これは心の病気だけでなく、長期間の過労や睡眠不足などでも起こります。
慢性的なストレスで不安が強まりやすくなる
ストレスが長く続くと、脳内の「セロトニン」という気分を安定させる神経伝達物質が減少してしまいます。
その結果、不安や落ち込みを感じやすくなり、ちょっとしたことでも過剰に反応してしまうのです。
「ちょっとした不安」が「強い不安」に変わるのは、脳内のバランスが崩れているサインかもしれません。
ストレスのケアを怠ると、将来的に精神疾患につながるリスクもあります。
急に不安感に襲われるのはなぜ?考えられる心の病気について
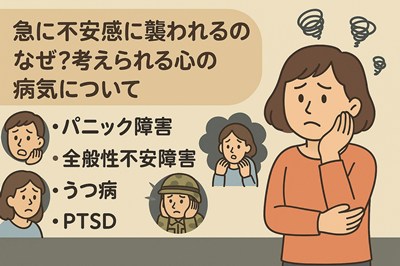
突然の不安感は、以下のような心の病気が背景にある場合もあります。
早めに気づくことが大切です。
パニック障害の可能性がある
パニック障害とは、突然強い不安に襲われる発作(パニック発作)を繰り返す病気です。
動悸や息切れ、胸の痛みなどの身体症状を伴うことも多く、「死んでしまうかも」という強い恐怖を感じます。
発作が起こる場所や状況を避けるようになり、生活範囲が狭くなってしまうこともあります。
詳しくは、厚生労働省のサイトでも紹介されています(厚生労働省|パニック障害)。
全般性不安障害の可能性がある
全般性不安障害は、日常的な出来事に対して過剰な不安を感じてしまう病気です。
心配しすぎる、悪いことばかり想像する、不安が止まらないといった状態が続きます。
「いつか何か悪いことが起きるのではないか」という考えにとらわれ、強いストレスを感じます。
不安が日常生活に支障をきたす場合は、医療機関の受診を検討しましょう。
うつ病の初期症状として出ることがある
うつ病は「気分が落ち込む」だけでなく、「理由のない不安」や「イライラ」といった症状も含まれます。
最初は不安感として始まり、徐々に意欲の低下や思考力の低下が見られるようになることもあります。
「今まで楽しめていたことが楽しく感じない」などの兆候がある場合、うつ病の可能性も視野に入れてください。
うつ病についての詳しい情報は、国立精神・神経医療研究センターのページが参考になります(NCNP|うつ病について)。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)の可能性がある
PTSDは、過去に体験した強いショックや恐怖が原因で、不安やフラッシュバックなどの症状が出る病気です。
似たような状況に直面したときに急に不安感に襲われることがあります。
PTSDは放置しておくと、心だけでなく身体にも悪影響を及ぼすため、早めの対応が必要です。
日本トラウマティック・ストレス学会などでも、理解と支援の重要性が述べられています。
急に不安感に襲われるのはなぜ?身体の不調が原因のケースも

心の問題だけでなく、体の病気が隠れている場合もあります。
身体的な異常が不安感として表れることがあるため、注意が必要です。
甲状腺の病気が原因の場合
甲状腺ホルモンが過剰に分泌される「バセドウ病」などでは、心拍数が増えたり、不安感や焦燥感が強くなることがあります。
この症状は、精神疾患と間違えられることも多く、正しい診断が重要です。
血液検査で簡単にホルモンの異常がわかるため、内科や内分泌科を受診すると良いでしょう。
日本内分泌学会の解説も参考になります(日本内分泌学会|甲状腺の病気)。
低血糖で不安感が出ること
糖質制限をしていたり、食事を抜いたりすると血糖値が急激に下がることがあります。
低血糖になると脳にエネルギーが行き届かず、めまいや不安感、震えなどが出ることがあります。
これを「低血糖発作」と呼び、特に糖尿病の薬を使っている方は注意が必要です。
日本糖尿病学会では、低血糖時の注意点について詳しく説明しています(日本糖尿病学会|低血糖について)。
心臓の不整脈などが関係
突然の動悸や息切れ、不安感がある場合、心臓のリズムに異常がある「不整脈」の可能性があります。
不整脈は一時的なものもありますが、命に関わる場合もあるため軽視できません。
不安感が強く、同時に胸の痛みやふらつきがある場合は早めに循環器内科を受診しましょう。
日本循環器学会のホームページにも詳しい情報があります(日本循環器学会|不整脈診療ガイドライン)。
生活習慣の乱れとの関係で急に不安感に襲われるのはなぜ?

生活習慣の乱れも不安感の大きな原因になります。
特に睡眠、食事、運動のバランスは心の健康に直結しています。
睡眠不足で脳が不安を感じやすくなる
睡眠は脳と心を休める大切な時間です。
睡眠不足が続くと脳が正しく働かなくなり、ちょっとしたことで強い不安を感じるようになります。
米国スタンフォード大学の研究でも、睡眠と不安の強い関連性が確認されています。
寝る前のスマホやカフェインの摂取を控えるなど、睡眠の質を高める工夫が必要です。
栄養の偏りが自律神経に影響する
栄養バランスが悪いと、脳内の神経伝達物質がうまく作られず、不安感やイライラが起こりやすくなります。
特にビタミンB群、マグネシウム、鉄分などは精神の安定に関係しています。
食事からの摂取が難しい場合は、医師に相談しながらサプリメントを活用するのも一つの方法です。
農林水産省の「食事バランスガイド」も参考にすると良いでしょう(農林水産省|食事バランスガイド)。
運動不足でストレス解消ができていない
運動には、ストレスホルモンである「コルチゾール」を下げ、幸福ホルモンの「セロトニン」を増やす効果があります。
運動をしないと、これらのホルモンバランスが崩れ、不安感が強まりやすくなります。
ウォーキングや軽いストレッチだけでも十分に効果があります。
運動不足が気になる人は、日常に無理なく取り入れられる方法を見つけてみましょう。
急に不安感に襲われた時の病院に行くべきサインとは

次のような症状がある場合は、自分だけで対処しようとせず、早めに医療機関を受診することが大切です。
日常生活に支障が出ている場合
不安感のせいで学校や仕事に行けない、家事が手につかないといった状態が続く場合は注意が必要です。
こうした場合、心の病気の可能性もあるため、早期に精神科や心療内科を受診しましょう。
医療機関検索は「こころの耳」などの公的サイトを活用すると便利です(こころの耳|働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)。
不安感が何日も続いている場合
一時的なものではなく、不安感が数日~数週間にわたって続く場合は病的な可能性があります。
我慢せず、心療内科や精神科に相談するのが良いでしょう。
放っておくと、不安がどんどん大きくなり、うつ症状に発展することもあります。
早期発見・早期対応が回復への近道です。
動悸や息苦しさなどの身体症状がある場合
不安とともに動悸、呼吸困難、手の震えなどがある場合は、身体的な病気が隠れている可能性もあります。
こうした身体症状は、不安障害やパニック障害などの典型的な症状です。
体調に異変を感じたときは、まず内科や心療内科に相談しましょう。
不安で眠れない状態が続く場合
睡眠は心の健康に欠かせません。不安感で寝つけない、途中で何度も目が覚めるなどの症状が続くと、精神的にも疲れてしまいます。
慢性的な不眠はうつ病や不安障害のサインであることもあるため、無理せず専門家に相談してください。
日本睡眠学会の情報も参考にできます(日本睡眠学会)。
急に不安感に襲われた場合の自分でできる対処法を紹介
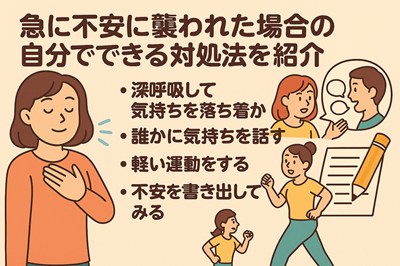
急な不安感に襲われたときに、すぐにできる対処法を知っておくと安心です。
深呼吸をして気持ちを落ち着ける
不安を感じたときは、ゆっくりとした深呼吸をすることで交感神経の興奮を抑えることができます。
鼻から4秒吸って、口から8秒かけて吐く「4-8呼吸法」がおすすめです。
深呼吸によって身体の緊張が和らぎ、不安感が軽減されます。
呼吸法の実演動画はYouTubeでも多数紹介されています(例:呼吸法の実践動画)。
誰かに気持ちを話す
心の中に不安を溜め込まず、信頼できる人に話すことで気持ちが軽くなります。
家族や友人、カウンセラーなど、安心できる相手を見つけて話すことが大切です。
言葉にするだけでも、自分の感情を客観的に捉えることができ、不安の正体が見えてきます。
話せる相手がいないときは、電話相談も活用しましょう(例:厚生労働省|電話相談一覧)。
軽い運動をする
軽く体を動かすことで、脳内のセロトニンが分泌され、気分が落ち着いてきます。
ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、無理のない運動を日常に取り入れてみましょう。
「運動をしよう」と思うだけでも前向きな気持ちが芽生えます。
継続することがポイントです。
不安を書き出してみる
不安を紙に書き出すことで、自分の中で整理され、客観的に考えるきっかけになります。
「今何が不安なのか」「その不安は本当に起きる可能性があるのか」と自問自答してみましょう。
書くことで、頭の中の混乱が落ち着き、不安の正体が見えてきます。
日記やメモ帳でもOKです。
リラックスできる音楽を聴く
ゆったりした音楽や自然音を聴くことで、副交感神経が優位になり、不安感がやわらぎます。
YouTubeには「リラックス音楽」や「睡眠導入BGM」などのチャンネルが多数あります。
自分が安心できる音を見つけて、日常的に取り入れてみましょう。
おすすめ:癒しの音楽チャンネル
急に不安感に襲われるのはなぜ?周囲の人にできるサポートとは

身近に不安感を訴える人がいた場合、どう接すればよいか悩む方も多いはずです。
以下のポイントを押さえて支援していきましょう。
話を否定せずに聞く
「そんなこと気にしなくていいよ」と言ってしまうと、相手は理解されていないと感じます。
まずはじっくり話を聞き、「そう感じるんだね」と受け止める姿勢が大切です。
共感するだけでも、相手の気持ちはずいぶんと楽になります。
聞き役に徹することが支援の第一歩です。
無理に励まさない
「頑張って」や「気にしすぎだよ」といった言葉は、かえってプレッシャーになります。
本人が不安を感じていることを否定せず、そのまま受け入れてあげることが大切です。
必要であれば、専門家への相談を一緒に促してあげましょう。
一緒に病院を探してあげる
不安を感じている人は、何かを「決める」「行動する」ということ自体に負担を感じている場合があります。
一緒に心療内科やカウンセリングルームを探してあげることで、少しずつ安心感が生まれます。
予約や付き添いも可能であれば行ってあげると、より心強く感じられます。
安心できる環境をつくる
不安が強いときは、安心できる「居場所」の存在が非常に重要です。
静かで落ち着いた場所や、自分らしくいられる空間をつくってあげると安心感が得られます。
家族や友人との穏やかな時間が、不安をやわらげる大きな支えになります。
まとめ|急に不安感に襲われるのはなぜ?原因を知って正しく対処しよう

急な不安感には、ストレスや過去の体験、生活習慣、身体や心の病気など、さまざまな原因が考えられます。
まずは自分自身の状態を知り、必要に応じて専門家の力を借りることが大切です。
不安感は決して「弱さ」ではありません。正しく向き合えば、必ず楽になります。
今日から少しずつ、自分と向き合う時間を大切にしてみましょう。



