人間関係がうまくいかない、自分だけが心を開けないと感じていませんか?
「人を信じられない」という気持ちは、多くの人が抱える深刻な悩みです。
本記事では、なぜ人を信じられないのか、その背景や共通する特徴、そして日常生活での生きづらさについて詳しく解説します。
さらに、カウンセラーの視点から、人間関係を楽にするための具体的な克服法や行動のヒントを紹介します。
なぜ人を信じられないと感じるのか?その背景とは

人を信じられない理由はさまざまですが、多くの場合、心の中にある過去の経験や価値観が関係しています。
以下では、信じられなくなる原因としてよく見られる背景を解説します。
過去の裏切りやトラウマが原因だから
人を信じることができなくなった背景には、過去の裏切りや心の傷が関係していることが多いです。
例えば、親しい友人や恋人から裏切られた経験や、いじめ、虐待といった強いストレス体験は、人間不信を招きます。
こうしたトラウマは、心の奥に強く残り、無意識のうちに人と距離を取るようになります。
精神的外傷の影響については、厚生労働省「こころもメンテしよう」に詳しく記載されています。
幼少期の家庭環境が影響しているから
子どものころの家庭環境は、その後の人間関係の土台になります。
親からの愛情不足、過干渉、家庭内不和などがあると、人との信頼関係を築く力が育ちにくくなります。
特に、親が感情をコントロールできない家庭で育つと、他人の感情も信用できなくなりがちです。
これは「愛着障害」と呼ばれ、NHKハートネットでも特集されています。
自己肯定感が低いと他人を信じにくくなるから
自分に自信がないと、他人に対しても素直になれません。
「自分なんて信用されない」「どうせ裏切られる」といった思考は、他者への信頼を妨げます。
自己肯定感が低い人ほど、人からの好意を疑ってしまい、孤立しやすくなります。
自己肯定感については、文部科学省の調査結果にも言及されています。
人間関係で傷つく経験が繰り返されたから
人間関係で何度も傷つくと、「もう誰も信じない」と心を閉ざしてしまいます。
特に、努力して人と関わろうとしても、失敗ばかりが続くと、無力感や不信感が強くなります。
それがやがて、「信じること=傷つくこと」という誤った認識に変わってしまうのです。
このような思考のクセは、時間と共に定着してしまうため、早めのケアが大切です。
人を信じられない人に共通する特徴とは
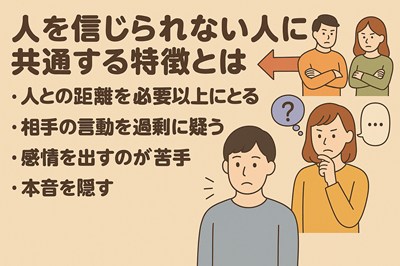
人を信じられない人には、いくつか共通する行動や思考パターンがあります。
これらの特徴を知ることで、自分の状態を客観的に見つめ直すきっかけになります。
人との距離を必要以上に取ろうとする
信じることに不安を感じる人は、他人と深く関わることを避けがちです。
相手に本音を話すことを避け、表面的な付き合いだけで済ませようとします。
これは「安全距離」を保つための無意識な防衛行動です。
結果として孤立を深め、人間関係の幅も狭くなってしまいます。
相手の言動を過剰に疑ってしまう
「本当に自分のことを思ってくれているのか?」と、常に相手の意図を疑ってしまう傾向があります。
たとえ善意であっても裏があると考えてしまい、素直に受け入れることができません。
このような疑い深さは、関係性の悪化を招きやすくなります。
特に職場や恋人との関係において、摩擦の原因となることもあります。
感情を表に出すのが苦手
人を信じられない人は、自分の感情を隠そうとします。
喜びや悲しみを人前で見せることに抵抗があり、常に「平常心」を装います。
しかし、感情を出さないことは決して強さではありません。
むしろ、相手との信頼関係を築くうえでマイナスに働くことも多いのです。
自分の本音を隠す傾向がある
「こんなこと言ったら嫌われるかも」と考え、本音を口に出すことができません。
自分の気持ちを押し殺し、相手に合わせることで、表面的な関係を保とうとします。
しかし、そのような関係は疲れやすく、心の距離は縮まりません。
本音を言える関係が、人間関係の質を高める鍵となります。
人を信じられないことで感じる生きづらさについて
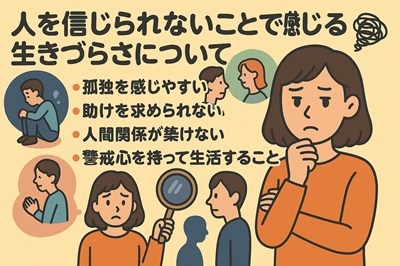
人を信じられないという感情は、日常生活にさまざまな影響を与えます。
ここでは、信頼できる人がいない状態で感じる代表的な「生きづらさ」について見ていきましょう。
孤独を感じやすくなる
信じることができないと、心を許せる相手がいなくなります。
そのため、たとえ周囲に人がいても、孤独感が強まります。
孤独が慢性化すると、精神的な健康にも悪影響を及ぼします。
内閣府「孤独・孤立対策」でも、孤独の健康リスクについて警鐘が鳴らされています。
助けを求められなくなる
困ったときに誰かに相談することが難しくなります。
「迷惑をかけたくない」「どうせ理解されない」と思ってしまい、1人で抱え込んでしまいます。
これがストレスの蓄積につながり、心身のバランスを崩す原因となります。
助けを求める力も、「信じる力」の一部です。
職場や学校で人間関係が築けない
人間関係が築けないと、職場や学校で孤立しやすくなります。
必要以上に緊張し、誰とも打ち解けられないまま時間だけが過ぎていきます。
その結果、成果にも影響し、評価や自己肯定感の低下へとつながります。
特にチームワークが求められる環境では大きなハンデとなります。
常に警戒心を持って生活することになる
「誰かに騙されるかもしれない」という意識が抜けず、いつも警戒モードで過ごすことになります。
この状態が長く続くと、心が休まらず、慢性的な疲れや不眠に悩まされるようになります。
安心して暮らすには、ある程度「人を信じる」力も必要です。
心の安全基地がないことは、大きなストレスの原因になります。
人を信じられない人が人間関係で直面しやすい問題

信じることができない状態は、具体的な人間関係のトラブルとして現れやすくなります。
ここでは、人を信じられないことで起こりやすい問題を見ていきます。
友人関係が長続きしにくい
「本当の自分を見せたら嫌われる」と思い込み、距離を縮めることができません。
また、相手の些細な行動にも不信感を持ちやすく、関係を自ら終わらせてしまうこともあります。
そのため、表面的な関係ばかりが増え、長く付き合える友人を持つことが難しくなります。
深い信頼関係を築くには、リスクを受け入れる勇気も必要です。
恋愛関係で不安が強くなる
恋愛においても、信じられないという気持ちは強く影響します。
「浮気されるかも」「本気で愛してくれていないかも」といった不安が絶えません。
過剰な束縛や確認行為などで、相手との信頼関係を壊してしまうこともあります。
心理的な不安が恋愛に与える影響は、国立精神・神経医療研究センターでも取り上げられています。
職場で孤立しやすい
職場では、信頼関係が仕事の効率や成果にも直結します。
しかし、人を信じられない人はチームワークを苦手とし、単独行動を好みがちです。
その結果、協力を得られず孤立しやすくなります。
孤立は、ストレスやモチベーションの低下にもつながります。
周囲から誤解されやすい
人と距離を置いたり、感情を表に出さなかったりすると、冷たい人・関わりづらい人と思われがちです。
実際には心の中で不安と葛藤しているにも関わらず、誤解されやすいのです。
こうしたギャップがさらなる孤立を生み、「やっぱり誰も信じられない」と思ってしまいます。
人間関係における非言語コミュニケーションも重要な要素です。
人を信じられない状態が続くとどうなる?心と体への影響
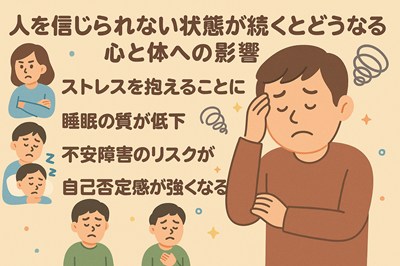
人を信じられないという状態は、心だけでなく体にも悪影響を及ぼします。
ここではそのリスクについて、精神面と身体面の両面から解説します。
慢性的なストレスを抱えるようになる
常に人間関係に緊張や不安を感じていると、自律神経が乱れ、ストレスが蓄積します。
ストレスホルモンが長期間分泌されると、免疫力が低下し、病気にもかかりやすくなります。
厚生労働省のe-ヘルスネットによると、ストレスは高血圧や糖尿病などの生活習慣病の要因にもなります。
ストレス対策には、心のケアと信頼関係の構築が欠かせません。
睡眠の質が低下する
警戒心が強いままだと、夜になっても気が抜けず、熟睡できなくなります。
寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりといった不眠の症状が現れやすくなります。
睡眠の質が低下すると、集中力や判断力にも悪影響を及ぼします。
睡眠とメンタルヘルスの関係は、国立精神・神経医療研究センター病院 睡眠障害センターでも詳しく紹介されています。
うつや不安障害のリスクが高まる
人間関係の不安が続くと、うつ病や不安障害といった精神疾患を引き起こすリスクが高まります。
特に、社会的孤立や慢性的ストレスが続くと、気分の落ち込みが慢性化する恐れがあります。
こうした病気は「甘え」ではなく、医学的に治療が必要な状態です。
早めに医療機関やカウンセリングを受けることが大切です。
自己否定感が強くなる
「信じることができない自分はダメだ」と、自分を責める気持ちが強くなります。
また、人とうまくいかない経験が積み重なることで、ますます自分を否定するようになります。
この悪循環は、自己肯定感のさらなる低下を招きます。
回復には、まず自分を責める気持ちを和らげることから始めましょう。
カウンセラーが教える、人を信じられない気持ちの克服法
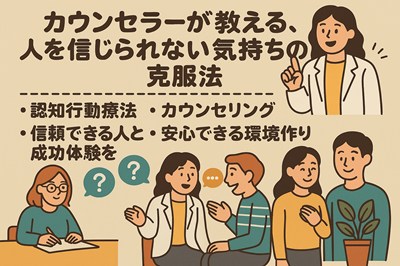
人を信じる力は、少しずつ育てていくことができます。
ここでは、心理カウンセラーが実際に使う信頼関係の回復に役立つ方法をご紹介します。
認知行動療法で思考のクセを見直す
認知行動療法(CBT)は、思考パターンを整理し、現実的な視点を取り戻すための心理療法です。
「どうせ裏切られる」という思考を、「本当にそうだろうか?」と検証する練習を行います。
客観的に物事を見る力をつけることで、不安や恐れを軽減できます。
CBTについて詳しくは、日本認知・行動療法学会のサイトをご覧ください。
カウンセリングで安心できる関係を体験する
カウンセリングは、信頼できる関係の「安全な練習場」とも言えます。
安心して本音を話せる経験を重ねることで、「信じても大丈夫かもしれない」という気持ちが芽生えてきます。
また、過去の傷ついた経験を言葉にすることで、気持ちの整理も進みます。
1人で抱え込まず、専門家の力を借りることはとても大切です。
信頼できる人との小さな成功体験を重ねる
いきなり全てを信じるのではなく、小さな約束やお願いを通じて、少しずつ信頼を築いていく方法があります。
たとえば、「今日の予定を共有する」「返事をもらう」といった日常のやりとりでも十分です。
小さな「大丈夫だった」が積み重なると、自信と安心感につながっていきます。
大切なのは、成功体験を積極的に意識することです。
安心できる環境を意識的に選ぶ
信頼関係を築くには、まず安心できる場に身を置くことが大切です。
攻撃的な人やストレスの多い場所では、信じる力も育ちにくくなります。
人の優しさや思いやりを感じられる環境を、自分の意志で選んでいきましょう。
自分を守る行動も、信じることへの第一歩です。
人を信じられない自分と向き合うためにできること

人を信じられない自分を責めるのではなく、「なぜそうなったのか」を丁寧に見つめ直すことが大切です。
ここでは、自分と向き合うための具体的な方法を紹介します。
自分の気持ちを紙に書き出してみる
言葉にならないモヤモヤした気持ちは、紙に書くことで整理されていきます。
自分の中にある「不安」や「怒り」「悲しみ」を正直に書き出してみましょう。
誰にも見せる必要はありません。書きながら、自分の本当の気持ちに気づけることがあります。
書くことによる自己理解の促進効果は、日本健康心理学会の研究でも示されています。
なぜ信じられないのか自分に問いかける
「なぜ自分は信じることが怖いのか?」と自分自身に問いかけてみましょう。
過去の出来事、誰かの言葉、失敗経験など、何かしらの原因があるはずです。
原因が明確になれば、それに対処する方法も見えてきます。
無意識にフタをしていた記憶と向き合うことが、癒しの第一歩です。
失敗を恐れず人と関わる機会を増やす
信じる力は、経験を通じて少しずつ育つものです。
失敗を恐れて関わりを避けていると、いつまでも不信感は変わりません。
小さな会話、短い時間の交流から始めて、人と関わる機会を増やしてみましょう。
思い切って一歩踏み出すことで、新しい発見があるかもしれません。
過去の自分を責めすぎないようにする
「あの時もっと上手くやっていれば…」と過去の自分を責めても、前には進めません。
そのときの自分なりに精一杯だった、ということを認めてあげましょう。
過去を受け入れることで、今の自分を肯定することができるようになります。
セルフコンパッション(自分への思いやり)の重要性は、心理学の研究でも注目されています。
人を信じられない人に試してほしい小さな一歩

いきなり誰かを信じることは難しくても、「ちょっとした行動」ならすぐに始められます。
ここでは、毎日の中でできる信頼回復のための小さな行動を紹介します。
「ありがとう」や「ごめんね」を言葉にする
感謝や謝罪の言葉を口に出すことは、信頼の第一歩です。
たとえ短い一言でも、相手との関係を少しずつあたたかくしていきます。
言葉には力があります。自分の感情を表現する練習にもなります。
小さな勇気が、大きな信頼につながることもあるのです。
挨拶や笑顔を意識してみる
挨拶や笑顔は、信頼関係を築くためのシンプルで効果的な手段です。
言葉を交わさなくても、笑顔だけで相手の警戒心を和らげることができます。
最初はぎこちなくても構いません。繰り返すことで自然な表情になります。
自分自身も気持ちが明るくなっていくはずです。
SNSで共感できる人の投稿を見てみる
実際に人と関わるのが難しいときは、SNSを活用するのも一つの方法です。
同じような悩みを抱えている人の投稿を見て、「自分だけじゃない」と感じられます。
特に、心理カウンセラーや専門家が運営するアカウントには有益な情報が多く発信されています。
匿名性のある空間だからこそ、安心して見られることもあります。
短い時間でも人と関わる習慣を作る
信頼を育てるには、「接触頻度」も重要です。
数分の雑談、買い物時のやりとりなど、日常の小さな関わりを大切にしてみましょう。
人と関わることが「特別なこと」ではなく、「日常」に変わっていくと、不安も和らぎます。
続けることで、信じる力は少しずつ育っていきます。
人を信じられない気持ちを理解してくれる人の見つけ方

信頼できる人を見つけるには、自分の気持ちを受け止めてくれる「安全な相手」と出会うことが大切です。
ここでは、そうした人とつながるための具体的な手段を紹介します。
心理カウンセリングを利用する
カウンセリングは、自分の気持ちを安心して話せる場所です。
資格を持った専門家が、偏見なく話を聞いてくれるため、「こんなこと話してもいいのかな」という不安も少なくて済みます。
日本臨床心理士会のサイトでは、信頼できるカウンセラーを探すことができます。
一人で抱えずに、専門家に頼るのは大切な勇気です。
生きづらさに寄り添うSNSコミュニティを探す
最近では、「人間関係が苦手」「信じるのが怖い」と感じる人たちのSNSコミュニティも増えています。
匿名で気軽にやりとりできるため、初めての方でも安心です。
共感されることで、「自分はおかしくない」と感じられるようになります。
自助グループやピアサポート団体の情報も役立ちます。
信頼を大切にするNPO団体やサロンを活用する
NPO団体の中には、安心できる居場所づくりを目的とした活動を行っているところもあります。
たとえば、NPO法人コモンズなどは、信頼関係の構築に力を入れています。
こうした団体のイベントやワークショップに参加することで、信頼できる人と出会えることもあります。
社会とのつながりを持つことが、自己回復にもつながります。
家族や友人に正直に気持ちを伝えてみる
「人を信じられない」という気持ちを、身近な人に少しだけでも打ち明けてみましょう。
理解されることで、心の荷が少し軽くなるはずです。
たとえ完璧にわかってもらえなくても、「話せたこと」自体が大きな一歩です。
信頼は「共有」から始まります。
まとめ|人を信じられない人の特徴と生きづらさ、克服へのヒント

人を信じられないことには、必ず理由があります。過去の傷、育った環境、自分への自信のなさなど、さまざまな背景があるでしょう。
しかし、それは決して変えられないものではありません。少しずつ自分を知り、行動を変えていくことで、信じる力は取り戻せます。
大切なのは、「信じたい」と思うその気持ちを、まずは自分自身が信じてあげることです。
あなたは一人ではありません。今日できる小さな一歩を、ぜひ踏み出してみてください。


