「なんだか毎日がしんどい」「うまくいかないことばかり」そんなふうに感じたことはありませんか?
この記事では、なぜ「生きずらい」と感じるのか、その原因を深掘りし、自分自身と向き合うための自己分析の方法を紹介します。
心のモヤモヤを少しでも軽くするためのヒントや、すぐに実践できる行動も解説しています。
一人で抱え込まず、まずは自分の気持ちを理解するところから始めてみましょう。
なぜ「生きずらい」と感じるのか?その原因を探る

人が「生きずらい」と感じるのには様々な理由があります。
まずはその代表的な原因を見ていきましょう。
人間関係がうまくいかないから
友達や家族、職場の同僚など、人間関係のストレスは「生きずらさ」を感じる大きな原因の一つです。
うまく話せなかったり、誤解されたり、相手の期待に応えようとして疲れてしまうこともあります。
また、「嫌われたくない」という気持ちが強すぎると、自分を押し殺してしまうこともあります。
それが続くと、徐々に心がすり減っていき、生きづらさを感じやすくなります。
学校や仕事に適応できないから
学校ではテストの成績や友人関係、仕事では業務のプレッシャーや職場のルールが原因で、「自分は合っていないのでは」と感じることがあります。
実際、文部科学省によると2022年度の不登校児童生徒は約30万人と過去最多を記録しています(文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等調査」)。
こうしたデータは、「適応できない」と感じるのはあなただけではないということを示しています。
無理に合わせようとするより、自分に合った環境や方法を探ることが大切です。
自己肯定感が低いから
「どうせ自分なんて…」「自分には価値がない」そんなふうに思ってしまうと、生きること自体がつらく感じてしまいます。
自己肯定感が低い人は、自分の長所に気づきにくく、失敗ばかりに目がいきがちです。
実際、内閣府の調査では日本の若者は欧米諸国に比べて自己肯定感が低い傾向にあるとされています(内閣府「令和4年版子供・若者白書」)。
まずは自分のよいところを一つでも見つけて、認めることから始めましょう。
過去のトラウマが影響しているから
過去に受けた心の傷やつらい体験が、今の自分の行動や思考に影響を与えていることもあります。
これは「心の傷(トラウマ)」と呼ばれ、無意識のうちに自己防衛のための行動パターンを生んでいることがあります。
専門機関ではトラウマケアのプログラムも提供されており、日本トラウマティック・ストレス学会などが信頼できる情報源です。
トラウマは無理に忘れるのではなく、向き合うことで乗り越えることができます。
発達特性やHSPの可能性があるから
「普通のことなのにどうしてこんなに疲れるんだろう」と思った経験はありませんか?
もしかすると、発達特性(ADHD・ASD)やHSP(繊細な気質)の可能性があるかもしれません。
HSPとは「Highly Sensitive Person」の略で、感受性が高く、周囲の刺激に敏感な人のことです。
参考として、HSP研究所などのサイトでは、詳しい説明や自己診断ツールが掲載されています。
一人で悩まず、特性を知ることから始めてみましょう。
「生きずらい」と思う気持ちは自分だけじゃない

「自分だけがつらいのでは」と思うこともあるかもしれませんが、同じように悩む人はたくさんいます。
SNSや検索ワードでも多くの人が同じ悩みを抱えている
TwitterやInstagramなどのSNSでは、「#生きづらい」「#HSP」「#つらい」などのハッシュタグで多くの投稿が見られます。
Googleトレンドで「生きづらい」と検索すると、一定の頻度で検索されていることがわかります(Googleトレンドで確認する)。
つまり、あなただけが感じているのではなく、多くの人が同じ悩みを抱えているのです。
そうした「見えないつながり」があるだけでも、少し心が軽くなるかもしれません。
厚生労働省の調査でもストレスを感じる人が多い
厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、日本人の約6割が日常生活でストレスを感じていると報告されています(厚生労働省:国民生活基礎調査)。
学校や仕事、人間関係の中で「しんどさ」を感じるのはとても自然なことなのです。
大切なのは、それをどう乗り越えるかという視点です。
周囲の人やサービスを活用しながら、少しずつ進んでいきましょう。
共感してくれるコミュニティやカウンセリングサービスがある
「自分だけじゃない」と感じられる場所として、共感型のオンラインコミュニティや、LINEで相談できるサービスも増えています。
あなたのいばしょなどは、匿名で気軽に相談できる窓口です。
人と話すことが苦手な方でも、文字で気持ちを伝えることで安心感を得られるかもしれません。
誰かとつながることが、悩みからの第一歩になるのです。
「生きずらい」と感じる人に共通する考え方や行動パターン

「生きずらさ」を抱える人には、ある共通の考え方や行動パターンが見られることがあります。
自分の傾向を理解することが、気持ちを軽くする第一歩になります。
完璧主義になりすぎる
「失敗したらダメ」「ちゃんとやらなきゃ」と考えすぎてしまう人は、無意識のうちに完璧主義になっている可能性があります。
これは「0か100か」で物事を判断しがちな思考パターンで、少しでもうまくいかないと自己否定に陥ってしまいます。
「まあまあでOK」と思えることが、心の負担を減らすコツです。
心理学ではこれを「認知のゆがみ」と呼び、認知行動療法などで改善するアプローチもあります。
他人と比べすぎてしまう
SNSなどを見て、「あの人はすごいな」「自分は全然ダメだ」と感じたことはありませんか?
人と比べることはモチベーションにもなりますが、過剰になると自己否定の原因になります。
特にSNSでは、他人の「良いところ」ばかりが見えるため、現実との差を感じて落ち込みやすくなります。
自分のペースを大切にし、昨日の自分と比べるように意識を変えてみましょう。
感情をうまく表現できない
つらい、悲しい、うれしいといった気持ちを言葉にできないと、周囲とのコミュニケーションも難しくなります。
これにより「わかってもらえない」と感じてしまい、孤独感が強まることがあります。
「うまく話せない」は悪いことではありません。まずは紙に書くところから始めてみましょう。
「感情日記」や「ジャーナリング」などの手法が、感情の整理に効果的です。
「~すべき」にとらわれすぎている
「○○すべき」「こうあるべき」という考えが強すぎると、自分を追い込んでしまうことがあります。
これは「べき思考」と呼ばれ、過度な自己要求が生きづらさにつながります。
もっと自由で柔軟な考え方を身につけることで、自分を縛らずに済みます。
「してもいい」「しなくてもいい」という思考に切り替える練習をしてみましょう。
自己分析で「生きずらい」原因を見つける方法
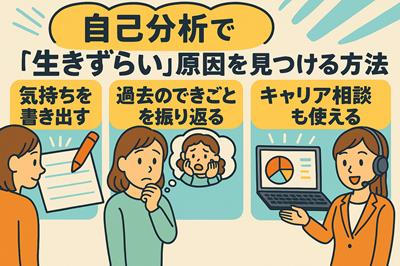
「どうして自分はこんなに生きづらいのか?」と感じたとき、自分を見つめ直す方法が自己分析です。簡単にできる方法をいくつか紹介します。
モヤモヤした気持ちを紙に書き出す
まずは自分の気持ちや思っていることを、紙に自由に書いてみましょう。
文字にすることで、自分の感情や思考のクセに気づくことができます。
頭の中がごちゃごちゃしているときこそ、書き出すことでスッキリします。
日記やメモアプリを使って、毎日少しずつでも続けてみましょう。
過去の出来事を振り返って共通点を探す
つらかった出来事、嬉しかった出来事を思い出し、ノートにまとめてみましょう。
そこに共通する「感情」や「状況」を見つけることで、自分の傾向が見えてきます。
例えば「否定されると落ち込む」「集団行動が苦手」など、パターンが明らかになります。
それを知ることが、次にどう対処するかを考えるヒントになります。
価値観マップやエニアグラムなどの診断ツールを活用する
自己理解のためには、心理テストや診断ツールを使うのも効果的です。
エニアグラム診断では、自分の性格タイプや価値観の特徴がわかります。
「価値観マップ」などを使うことで、自分が何を大切にしているかが明確になります。
診断の結果をもとに、自分らしい行動や選択を意識してみましょう。
就活生にも人気の「マジキャリ」などのキャリア相談を使える
マジキャリなどのキャリア相談サービスでは、専属のカウンセラーが一緒に自己分析を行ってくれます。
仕事だけでなく、生き方や性格の悩みまで相談できるため、自己理解に役立ちます。
「自分の強みがわからない」と感じている人にとって、第三者の視点はとても有効です。
無料相談もあるので、気軽に利用してみるのもよいでしょう。
「生きずらい」を改善するためにできる小さな一歩

すぐにすべてを変えるのは難しいかもしれません。
でも、小さな一歩を重ねることで、少しずつ「生きやすさ」は変わっていきます。
自分に優しい言葉をかける習慣をつける
「ダメだな」「なんでこんなこともできないんだ」と、自分を責めていませんか?
まずは「よく頑張ってるね」「大丈夫だよ」と自分に優しい言葉をかけることが大切です。
言葉には力があります。ポジティブな言葉を意識的に使うことで、気持ちも少しずつ前向きになります。
習慣にするために、寝る前に1つ、自分を褒める言葉を思い出してみましょう。
小さな成功体験を積み重ねる
いきなり大きな目標を達成しようとするのではなく、まずは「できたこと」を一つずつ増やしていきましょう。
例えば「朝起きられた」「散歩に行けた」など、どんなに小さなことでも成功です。
できたことをメモに残すと、自信につながります。
継続することで、自己肯定感も少しずつ高まっていきます。
疲れたときはしっかり休むようにする
現代社会では「頑張り続けること」が美徳とされがちですが、人は休まないとエネルギーが枯れてしまいます。
しっかり休むことで、心と体のバランスが整い、前向きな気持ちになれます。
眠れないときは、厚労省の睡眠改善ガイドも参考にしてみてください。
何もしない時間を大切にしましょう。
自分を否定しない考え方を身につける
失敗しても、自分のすべてがダメなわけではありません。
「たまたまうまくいかなかっただけ」「次に活かせる経験だった」と考えることで、前に進む力が生まれます。
自己否定が強いときは、カウンセラーに相談するのも一つの方法です。
考え方を少し変えるだけで、見える世界が変わることがあります。
「生きずらい」を和らげるために今すぐできること

何も大きなことをしなくても、今この瞬間からできる「心を軽くする行動」はたくさんあります。
深呼吸やストレッチなどで心と体を落ち着ける
緊張したり不安になったときは、まず深呼吸をしてみましょう。
ゆっくり息を吸って、ゆっくり吐くことで、自律神経が整い、心が落ち着きます。
体をゆっくり動かすストレッチも、心身のリラックスに効果的です。
YouTubeのストレッチ動画を見ながら試すのもおすすめです。
「生きずらい」と感じたときに頼れるサポートや相談先

「もう限界かも」と思ったとき、誰かに相談することは決して弱さではありません。
今は、匿名でも、無料でも、気軽に相談できる場所が増えています。
こころの健康相談統一ダイヤル
厚生労働省が全国共通で設置している、こころの健康相談統一ダイヤルは、精神的な悩みを抱えた人が、地域の保健所や精神保健福祉センターに相談できる窓口です。
電話番号は「0570-064-556」。
詳しくは厚労省公式ページをご覧ください。
特に緊急時や孤独を感じたときには、声を届けてくれる誰かがいるだけで安心できます。
厚生労働省の「まもろうよ こころ」
「まもろうよ こころ」は、厚生労働省が提供している心のケア情報ポータルサイトです。
悩みに応じた相談先の検索や、セルフチェック、リラックス法の紹介などが掲載されています。
信頼できる情報をもとに、自分に合ったサポートを探すことができます。
国が運営しているため、安心して利用できる点もポイントです。
LINEで気軽に相談できる「あなたのいばしょ」
「あなたのいばしょ」は、24時間365日、LINEで相談できる無料のサービスです。
話し相手が欲しい、孤独を感じる、ちょっと聞いてほしい。そんな時に、誰でも匿名で利用できます。
AIではなく人間が対応してくれるため、温かみのある対話が可能です。
スマホ一つで相談できる手軽さが、多くの利用者から高い評価を得ています。
学校や職場のカウンセラーに相談
学校にはスクールカウンセラー、職場には産業カウンセラーなど、専門の相談員が常駐していることがあります。
一人で抱える前に、まずは話してみることが重要です。
カウンセリングは問題を解決するためというより、「自分の考えや気持ちを整理する場」と考えるとよいでしょう。
話すことで見えてくることも多くあります。
まとめ|「生きずらい」原因を自己分析して、自分を理解する第一歩を踏み出そう
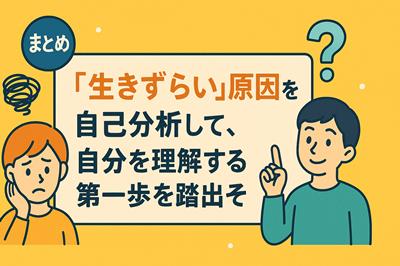
「生きずらい」と感じるのは、決してあなただけではありません。
人間関係や環境、自分の考え方など、さまざまな要因が絡み合っていることが多いです。
まずは自分の気持ちに向き合い、「なぜそう思うのか」を分析することから始めてみましょう。
小さな気づきが、少しずつ「生きやすさ」へとつながっていきます。
一人で頑張りすぎず、信頼できる人やサポートサービスに頼りながら、ゆっくりでも確実に前に進んでいきましょう。
そして何より、自分を責めずに、少しでも「自分を大切にする」時間を作ってください。それが、生きづらさを和らげる最初の一歩です。



